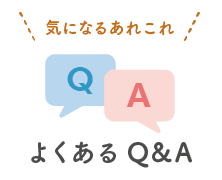永遠を見すえて
ルカによる福音書16章14~31節 牧師 鈴木光
神と富の両方に仕えることはできない、と語るイエス様をあざ笑う人々がいました。
1.神と富とを愛することはできない
あざ笑うのは「金に執着する」ファリサイ派の人々でした(14節)。「金に執着する」という言葉は、もっと直接的に訳せば「金の愛人」という単語です。
ファリサイ派の人々は表向きは旧約聖書の教えを厳密に守る立派な信仰者たちでしたが、実際は神様への愛や信仰のゆえにではなく、書かれた教えを守るという手段自体が目的になってしまっていました。ですから、形としては神様に従っていても、実際は金に仕えるように、内面的にはさまざまな偶像に従って生きていました。
イエス様は聖書の教えを逆手にとって、妻を離縁して愛人と再婚するような拡大解釈をする彼らの行動を例にあげて(18節)、神様を捨てて、金に仕えるような生き方を警告します。あなたは何を愛して生きるのか、が問われています。
2.永遠を見すえて生きる
続けてイエス様は「金持ちとラザロ」のたとえ話をします。ある金持ちは死んで「陰府(よみ)」に生き、苦しみを受けます。一方で貧しかったラザロは死んでアブラハムのいる天国に入れられます(22~23節)。これは生きている間の受けた物が死後に反映されるという話ではありません。
ポイントは「陰府」と訳されている元の言葉の「ハデス」にあります。ハデスは元々ギリシア神話の「死と富の神」の名前です。聖書において「陰府」は本来は裁きの苦しみがある地獄(ゲヘナ)とは違い、単なる死者のいる所を意味しますが、ここでは真の神様ではなく「富」を愛して裁きを受ける金持ちの姿にかけて表現しています。金をはじめとして、この世界のものを死の先に持ち込むことはできず、ただ滅びるだけです。しかし、主を愛する人はその先に永遠の至福の天国があります。永遠を見すえて生きる人は幸いです。
3.語られている言葉を聞いて応える
さて、たとえ話は続き、金持ちはせめて家族のもとにラザロを送って、彼らが悔い改めるように説得して欲しいと言います。しかし、既に聖書ではっきりと語られているのに聞かない人は、「たとえ死者の中から生き返るものがあっても、その言うことを聞き入れはしないだろう(31節)」と応えられます。時代も場所も超えて、今も聖書をとおして福音は語られています。今、聞いて応えるものになりましょう。
<思い巡らし>
何を愛し仕えているか/永遠を視野に入れて/聞いて応えるものに